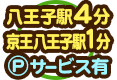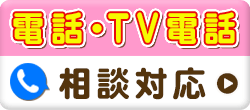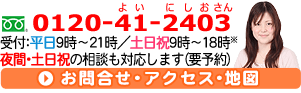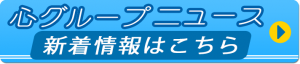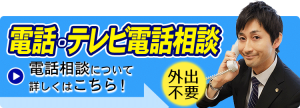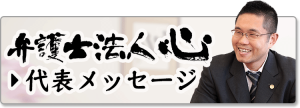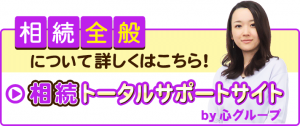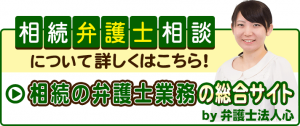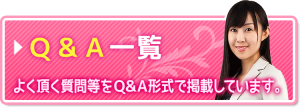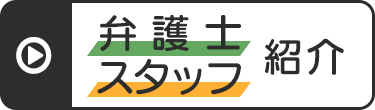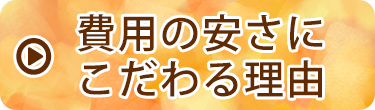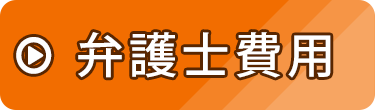最後に相続放棄をした人はどうなるか
1 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(=亡くなった方)の財産を一切引き継がないという意思表示を家庭裁判所に対して行う手続きのことをいいます。
一般的に、被相続人が借金や税金の滞納などの負債を抱えていた場合、その支払い義務を負わないように相続放棄の手続きがとられる場合が多いです。
また、近年では、被相続人は土地・建物を所有していたが、その管理・処分をすることが大変なため相続をしたくないとか、被相続人と生前の関係性が希薄であったため関わりあいたくないとして、相続放棄の手続きをとられる方もいらっしゃいます。
2 最後に相続放棄をした人はどうなるか
相続放棄は、相続人にとって被相続人の財産を引き継ぐことが負担になるような場合に利用される手続ですので、相続人全員が相続放棄をすることもよくあります。
では、最後に相続放棄をした人は、なにか負担・義務を負うことはあるのでしょうか。
⑴ 被相続人の財産は国庫に帰属する
まず、相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産は国に移ります。
しかし、相続人全員の相続放棄が完了したとしても、自動的に国庫に帰属するわけではなく、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人によって被相続人の財産を国庫へ帰属させる必要があります。
⑵ 相続放棄をした場合の相続財産の管理義務
従来の法律では、相続放棄をした場合であっても、相続財産管理人(後述の法改正で、「相続財産清算人」に名称が変更されました。)を選任してもらうまでは、相続財産の管理義務を負うこととなっていました。
したがって、被相続人が不動産を持っていた場合、相続放棄をしたとしても、相続財産管理人の選任手続きをしないまま放置してしまうと、万が一その家が破損・倒壊して第三者に損害が発生してしまった場合、損害賠償義務を負う可能性がありました。
しかし、令和5年4月に法改正があり、相続放棄をした時点で「現に占有」している相続財産についてのみ、管理義務を負うこととなりました。
したがって、被相続人が所有している家に一人暮らしをしていて、相続人は遠方に暮らしているといったケースでは、相続人は被相続人の家の管理義務を負わなくて済むことになりました。
他方で、被相続人が所有している家に同居している相続人などは、相続放棄をしたとしても依然として管理義務を負うことになりますので、義務を免れるためには相続財産清算人の選任手続きをとり、義務を引き継ぐ必要がありますので、注意が必要です。